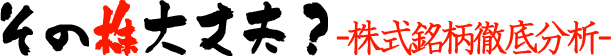
2021/06/12(土) 14:41:00投稿者:bwu*****
2021/06/12(土) 08:57:00投稿者:ウォーレン・バフェット
日本精機、3500人への職場接種申請 7月26日から実施
2021年6月10日
車載計器大手の日本精機は、従業員など3500人に対し、新型コロナウイルスワクチンの職場接種を実施する。7月12日の週にモデルナ製ワクチンが届くことを前提に、7月26日の週と翌週に1回目、8月23日の週と翌週に2回目の接種をする計画だ。
8日に申請した。従業員と工場内で働く取引会社社員などに新潟県長岡市内の2拠点で集団接種する。産業医、健康診断や人間ドックを担う医療機関などの複数ルートで医療人材を確保する計画だ。
ワクチンの職場や大学での接種は21日から始まる。新潟県内で申請した団体・企業数は8日時点で15、9日時点で21と増え、大手企業や大学などが申請を始めている。ただ、新潟市での高齢者向け接種の遅れが響き「教職員だけでなく、地域住民への接種も支援したいが、医療人材の確保が難しい」(新潟市内の大学のワクチン接種担当者)との声がある。新潟県は12日から乗り出す大規模接種で新潟市内の接種加速を急ぐ。
Appleから受注とれるか 部品メーカーに3つの新流儀
●HMIもハード丸ごと調達に
EVプラットフォームと並んで、新規参入組がハードを丸ごと調達したい領域が車内空間のHMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)である。車内デザインや独自の移動体験などで差異化したい企業にとっては生命線となる領域だ。
きづきアーキテクトの長島氏は「アップルカーは人の五感に訴えるような仕掛けをしてくるのでは」と予測する。ディスプレーやスピーカー、各種センサーなど、多くの部品をシームレスに組み合わせて新しいHMIを提供するには多くの技術やノウハウが要る。
ドイツや日本、米国など多くの高級車メーカーと1次部品メーカー(ティア1)の立場でHMI開発をしてきたアルプスアルパイン社長の栗山年弘氏は、「HMIはコモディティー化しない。現状でも自動車メーカーごとに全部違うが、個性が出てくる領域だ」と見通す。世界の高級車メーカーとティア1として長く付き合い、ブランドごとにHMIを造り分けてきた実績が強みになるという。
ティア1としての提案力を高めるため、アルプスアルパインは車載メーター大手の日本精機と資本業務提携するなど他社との連携を加速させる。技術を持ち寄って「統合コックピット」の開発を進めるためだ。
2021/06/12(土) 08:48:00投稿者:損切り王子
来週は期待していいかな?
2021/06/11(金) 15:54:00投稿者:owop
株価の予想は不可能。
2021/06/11(金) 15:41:00投稿者:ウォーレン・バフェット
新中長期経営計画方針のお知らせ(2021年~2023年)
車載事業の経営基盤強化と、サービスを含む事業間連携による新しいビジネスの創造
1収益力の強化
2経営の効率化
3新規ビジネスの実現
2023年度目標
売上高 2,650億円 営業利益 132億円(5%)
・車載計器事業
主力事業による安定収益基盤の構築(HUD事業の拡大、コスト競争力の強化など)
・コンポーネント事業(民生機器)
車載の高信頼性を活かした顧客価値の最大化(顧客ニーズに適したソリューション提案など)
・樹脂材料事業(着色・コンパウンド)
透明系樹脂を核とした売上拡大(高機能樹脂材料リサイクル技術の実現など)
・ディーラー事業
地域に密着した事業拡大(顧客の囲い込み、サービスの向上、オペレーションコストの低減など)
・その他事業(情報システム/物流/広告/食彩)
サービス事業の収益拡大(IT・物流・広告などの事業連携による新サービスの創出など)
アルプスアルパインとの資本業務提携により、新たな価値の創出
■競合他社と差別化した製品を創出
■利用者に今まで経験したことのない
使い勝手の良さや質感を提供
■2024年度からのビジネス寄与を目指す
エヌエスアドバンテックとエヌエスエレクトロニクスの合併により、一貫加工生産体制の構築
エヌエスアドバンテック(存続会社)・・・樹脂着色・成形、印刷
エヌエスエレクトロニクス・・・基板実装、外装ASSY
※両社共に二輪メータを製造
部品加工から製品組立まで1社での一貫生産
・四輪/二輪車用メータの生産集約により、ものづくり競争力向上
(製造・間接・バックオフィスの生産性向上、リードタイム短縮、スペース・在庫の効率化)
・四輪車用メータの組立を本社工場から移管し、本社工場はHUD生産・要素技術開発に注力
2021/06/11(金) 15:20:00投稿者:ウォーレン・バフェット
加えて、DMDには色の再現率が高いという強みもある。TFTは白色発光ダイオード(LED)にカラーフィルターを組み合わせており、色再現率を示すNTSC比は46%ほど。DMDはRGBの3色LEDと分割駆動によってNTSC比90%を実現できる。特に赤色がきれいに見えやすく、警告イラストといった注意喚起に使いやすい。
一方でDMDの課題はコストだ。Sクラス向けのDMDチップは対角0.55インチの専用設計品。現時点で米テキサス・インスツルメンツ(TI)以外の調達候補がないため、横展開などの大量生産を実現してもコスト削減には限度がある。
また、熱への対応策としてHUD機構の外装に当たるケースの材質を変更した。従来は樹脂成形品を採用していたが、太陽光の集光で高温になっても変形しにくいマグネシウム製に変えている。振動による変形も小さいため走行時のAR表示が安定しやすい。ケースは上下に分かれており、下部にPGUと補正鏡、凹面鏡を組み付け、上部をかぶせて構成している。
左右30度以上で歩行者に重ねる
日本精機はSクラスを皮切りにAR表示の研究開発を加速していく。現状の左右10×上下5度ではイラストを重ねられる範囲が道路上に限られるため、今後は歩行者までイラストを重ねて安全性の向上を狙う。
ただし、画角を左右と上下でそれぞれ2倍にできたとしても、表示距離10メートルでは景色の60~70%までカバーするのが限界だという。山谷氏は「歩行者にイラストを重ねて映すには左右30度以上が必要だ」と話す。
この高いハードルを越えるために同社は、自社での研究開発に加えて光学系の技術を持つスタートアップ企業との連携も視野に入れる。HUDの付加価値を高めるAR表示の技術に磨きをかけて、世界シェア首位の座を堅守する。
2021/06/11(金) 15:18:00投稿者:ウォーレン・バフェット
補正鏡と凹面鏡で拡大表示
DMDで生成した映像は、補正鏡と凹面鏡で2回反射させてフロントウインドーに投影している。補正鏡は特殊な「かまぼこのような形」(山谷氏)を成し、凹面鏡はA4サイズと大きく、縦方向の曲率を大きくして倍率を高めている。2種類の鏡はともに樹脂成形品で日本精機が内製する。
日本精機はこれら特殊な鏡を使って「クロス光学」と呼ぶ新技術を開発した。補正鏡を使って縦方向の光学系を一度実像で結像し、その実像の位置がかなり凹面鏡に近いため、凹面鏡で倍率を高めて短焦点でHUDの表示位置に虚像を結像させる。
新たな光学技術によって同等性能のHUDなら3割ほど機構の容量が減らせる計算だ。しかしながら、10メートル先に77インチ相当の映像を映すという性能上、機構の大型化は避けられなかった。
Sクラス向けのHUDは容量約20リットルで、GLE向けの約8リットルに比べて2.5倍の大きさだ。山谷氏は「Sクラスは開発当初からAR表示を念頭に置いていたため、搭載空間を何とか確保できた」と実情を明かす。
一般的なHUDでは、PGUに比較的安価なTFT(薄膜トランジスタ)液晶ディスプレーを使うことが多い。生成した映像は、HUD内部の平面鏡や凹面鏡で2回反射し、光路を稼ぎながら拡大してフロントウインドーに投影する。同方式の場合、3メートルほどの表示距離なら容量10リットル前後で収まる。
高倍率の光学技術には凹面鏡の集光で熱が大きく発生しやすい弱点もある。一般的なHUDならシステム全体の拡大倍率は5倍程度だが、Sクラス向けでは20倍まで拡大。従来のTFTでは熱に耐えられず「ボナンザ現象」と呼ぶ液晶の黒化が発生して、その部分の映像が抜けたように見えなくなる。
温度が下がれば元に戻るものの、表示コントラストの低下を招くため避けるべき現象だ。PGUに新採用したDMDは液晶ではないため同現象が起こらない。高倍率でも表示品位を安定して保てる。
2021/06/11(金) 15:17:00投稿者:ウォーレン・バフェット
日本精機執行役員HUD開発・設計本部本部長の山谷修一氏は「将来的には表示距離も可変して3次元的に見せたいが、現状は10メートル先に固定するのが最適解だ」と話す。
画角も広げている。GLE向けのHUDの画角は左右9×上下3度だった。アイボックス(運転者から表示映像が片目で視認できる大きさ)は横135×縦55ミリメートル。表示距離2.8メートルを掛け合わせると18.6インチ相当のサイズ感になる。Sクラス向けのHUDは画角を左右10×上下5度に広げ、アイボックスを横142×縦128ミリメートルに拡大。10メートル先に77インチの大画面を広げる。
ただ、表示距離を延ばして画角を広げることはHUD機構の巨大化を招く。例えば、表示距離を延ばすためには通常、機構内部で反射回数を増やして光路を延ばしたり、鏡の倍率を上げて拡大したりしている。いずれも部品の追加や大型化が必要になる。日本精機は今回、新たな光学技術の採用によって反射光路の拡大を抑えながら高倍率化に成功した。
抜本的に変えたのは映像の生成装置と鏡による反射技術だ。画像生成ユニット(PGU)には、同社初となるデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)を採用した。
DMDは多数の微細ミラーを平面に配列した表示素子。ミラーの数が画素数に相当し、それぞれのオンとオフを細かく制御して映像を描く。Sクラス向けのHUDは、約66万画素で微細ミラーの大きさは7.6マイクロ(マイクロは100万分の1)メートル角とする。
2021/06/11(金) 15:10:00投稿者:ウォーレン・バフェット
ベンツSクラス、HUDも怪物級 日本精機が巨大AR
2021年6月11日
クルマに拡張現実(AR)の本格適用が始まった。象徴的な例が、独ダイムラー「メルセデス・ベンツ」ブランドの旗艦セダン「Sクラス」だ
Sクラスは2020年下期の全面改良に合わせて、運転者の視点から10メートル先に77インチ相当の映像を表示し、一部イラストの位置を道路や前方車両に合わせて制御できるヘッド・アップ・ディスプレー(HUD)を搭載。現状の世界最高性能で「怪物級」といえる代物だ。実現技術を解き明かす
HUDは、主にステアリングホイール前方のインストルメントパネル(インパネ)部分に組み込む車載機器。車速や経路案内といった情報をイラストにして運転者の視点から数メートル先に映す。運転者は前方に向けた視線を動かすことなく必要な情報を得られるため、いわゆる「脇見運転」を減らせて安全性が高まる
SクラスはAR表示の適用でさらに安全な車両を目指した。例えば、経路案内の矢印を道路に重ねるように表示。運転者に次に取るべき操作を直感的に理解させる。また、前方車両の位置を示すイラストで追従機能の作動を分かりやすくする
SクラスのAR表示は一種の錯覚を利用している。表示距離は運転者の視点から10メートル先に固定して、イラストの大小を制御することで景色に重なっているかのように見せている。遠くは小さく、近くは大きく映すことで遠近感を生み出す
前方監視用のステレオカメラやミリ波レーダーで物体や道路の白線を検知して、対象物に合わせるようにイラストの大きさと位置を制御する。現状、運転者の視線をカメラで検知して表示を微調整するような仕組みは取り入れていない
表示距離×画角が鍵
Sクラス向けのHUDは、世界シェア首位の日本精機が開発・供給している。AR表示の鍵は表示距離と画角にあり、これらを掛け合わせたものが最終的な表示サイズに相当する。表示距離を延ばせればそれだけ前方の景色にイラストを重ねやすくなる。運転者は目のピント調整が楽になる。画角を拡大すればイラストを広範囲に動かしやすい
これまで日本精機はダイムラーの多目的スポーツ車(SUV)「GLE」向けにもHUDを供給、これが従来の上位モデルという位置付けだった。表示距離は運転者の視点から2.8メートルであり、今回の10メートルは距離を3倍超に延ばしたことになる
2021/06/11(金) 15:03:00投稿者:ウォーレン・バフェット
北米域の拠点再編による競争力向上 ~メキシコ連結子会社の合併と、米国販売会社の統括会社化~
当社は、北米地域に於ける、ものづくり競争力向上のため、2021年6月1日付で、メキシコに拠点を構える「ニッポンセイキ・デ・メヒコ社」、「ニッセイ・アドバンテック・メヒコ社」、「ニッセイ・ディスプレイ・メヒコ社」の3社(実質100%子会社)について、「ニッポンセイキ・デ・メヒコ社」を存続会社とした合併を行いました。併せて、米国ミシガン州の「エヌ・エス・インターナショナル社」を、北米地域の統括会社とすることで、北米地域全体の指揮・命令、情報の整流化とオペレーションの効率化を図ります。
日本精機グループは、グローバルでの自動車・オートバイ需要拡大に合わせ、世界各地に拠点を展開してまいりました。このたび、主力の四輪車用計器やヘッドアップディスプレイの生産比率が高い北米地域の、再編による合理化を図ることで競争力強化、収益性の更なる改善を目指します。
具体的には、メキシコ3社を合併し、四輪車用計器部品の加工、基板実装、組立、販売までを1社に集約することで、メキシコ地域に於ける一気通貫体制の整流化された“ものづくり”による競争力向上を図ります。また、「エヌ・エス・インターナショナル社」を北米地域の統括会社として、北米で製造を担う2社(米国オハイオ州の製造拠点「ニューサバイナインダストリーズ社」と「ニッポンセイキ・デ・メヒコ社」)に対する指揮・命令系統を一本化することで、迅速な意思決定を実現し、あわせて、北米各社で重複した機能の削減・解消、北米全体の基幹システム統合を進めることにより更なるオペレーション効率化を推進します。
日本精機グループは、経営基盤を更に強固なものとすることで、これからもお客様に価値の高い製品・サービスを提供してまいります。
89 :山師さん@トレード中:2021/01/28(木)19:10:24 ID:Axj2CE0l0.net
日本精機が引き受けてくれるならいいもの作れるね
 SAW(*ฅ•̀ω•́ฅ*)ガオー@SAW_saw_a_saw約8時間
SAW(*ฅ•̀ω•́ฅ*)ガオー@SAW_saw_a_saw約8時間ベンツSクラス、HUDも怪物級 日本精機が巨大AR
 にゃーこアッパーマス初級@turnip_stalk6月9日 15時05分
にゃーこアッパーマス初級@turnip_stalk6月9日 15時05分2021/06/09結果 キャノン、日本精機に加えて本日JFEが仲 …
 bunted@bunted6月9日 08時56分
bunted@bunted6月9日 08時56分日本精機 激GU気配
 MOTOMAN@bookpine6月9日 08時52分
MOTOMAN@bookpine6月9日 08時52分スタンレー、DMソリュ、エーザイ、S高気配。
 株情報・株トレード日誌@seigo776月9日 08時34分
株情報・株トレード日誌@seigo776月9日 08時34分7287 日本精機
 にゃーこアッパーマス初級@turnip_stalk6月9日 06時07分
にゃーこアッパーマス初級@turnip_stalk6月9日 06時07分いつもありがとう✨本田技研いつか欲しいんだけど今は割高だなーって思っ …
 にゃーこアッパーマス初級@turnip_stalk6月8日 15時28分
にゃーこアッパーマス初級@turnip_stalk6月8日 15時28分2021/06/8結果 昨日仲間入りしたキャノンと日本精機プラスで …
 にゃーこアッパーマス初級@turnip_stalk6月7日 15時23分
にゃーこアッパーマス初級@turnip_stalk6月7日 15時23分2021/06/7結果 東急の利確分にちょっと足してキャノンと日本 …
目先は大きく動きそう。相場と比較的高い相関関係がある。
対する空売り量で買い戻し余地拡大してるじゃなぃ??
https://acedthe.inatrupp.com/jgjceg/